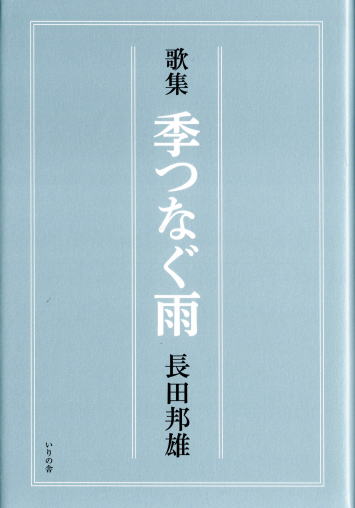長田邦雄歌集『季つなぐ雨』
深い悲しみを乗り越えて
仲田紘基
佐藤佐太郎、志満夫妻と並んで、津和野の森鷗外旧居の縁側にすわって写っている若き日の長田邦雄氏。写真の両端には佐保田芳訓氏と室積純夫氏のお姿も。この歌集の口絵に私はしばらく釘づけになった。「歩道」の軌跡にくっきり足跡の残るこの顔ぶれの中で、今も健在なのは著者だけである。
鷗外の旧居の縁に先生と坐りしことも遠くな
りたり
昭和五十九年より令和四年までの一千首を越える歌。三十九年間に及ぶ作歌から選んだ力作を収める長田氏の第二歌集『季つなぐ雨』は、氏の半生の貴重な歩みそのものでもあるだろう。
先生のみ棺担ふ庭の内しづかに重き空気淀め
る
放たれし矢の如く生きてわづかわづか四十三
歳に君は逝きたり
暑い夏の日、佐太郎家の庭の「重い空気」が伝わってくる一首目。二首目は親しい友人室積氏を悼む歌だが、この歌集が上梓されて間もなく、今度は佐保田氏とも別れることになる。
歌集には読むのが辛くなる歌も多いが、奥さんとの日常を詠んだ次のような歌にほっとさせられたりもする。
一年の生命を惜しむわが妻と桜満開の公園に
来つ
生まれくる孫思ひつつ服を編む妻の楽しみわ
れのよろこび
長田氏は技術を身につけ、受け継いだ店で研ぎ師としての人生を歩んでこられた。生業を題材としたものに印象深い歌が多い。
雪のふる気配床より足冷えて心忙しくわれは
仕事す
わがねむり浅きまま醒めて暁の街に出でたり
納品のため
いささかの技あるゆゑにわが請はれ生徒四十
名に研ぎ教へたり
かすかなるわが仕事さへ頼らるるゆゑに寒中
に包丁を研ぐ
しかし、歌集一巻を貫くのは、やはり著者の悲しみの思いだろうか。
からうじて残りし骨を骨壺に納めたる時心窮
まる
五百時間生きた長男への思い。それは何十年という長い歳月を経ても消えることのない悲しみであった。
長男として今あればいかならん納品の途次亡
き子思ひつ
ひと月に一度亡き子の墓参する慣おほよそ三
十年となる
後記に「私は多くの悲劇に遭遇し、実生活における苦悲は作歌をする活力を無くしていました。」とある。「悲劇」をみごとに乗り越え、むしろそれをバネに「実生活における苦悲」を”詩”として結晶させたのが歌集『季つなぐ雨』なのではなかろうか。読み応えのある重厚な歌集と言えよう。