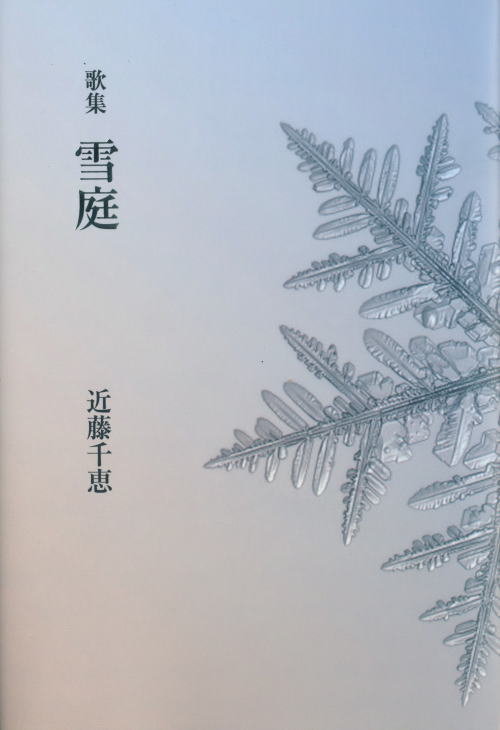歌集『雪庭』について 香川哲三
『雪庭』は近藤千恵さんの第三歌集であり、平成十五年から二十六年春までの作品四百六十五首が収められている。本集には、この間における近藤さんの生が、確かに刻まれており、そこから立ちのぼる気息には言い難い重みがある。人が生きてゆく上での作歌の意味ということを、私はこの一巻を通してしみじと考えさせられた。施設に暮らす夫を思い、また家族を見つめるなど、日々の過ぎ行きを様々に綴った作品と、折々に足を伸ばした旅先での作品が、殆ど境の無い詠風により静かに展開されてゆく。
春彼岸の草まだ萌えぬ土手ゆきて手にひやや
けき蕗の薹つむ
葦を吹く風に炎暑の匂ひあり久しく雨を待つ
梅雨の日に
立春のゆふべ茜の濃きそらを一群の雁つばら
かにゆく
近郷或いはお住い近くでの矚目だろうか。どれも穏やかな歌柄で言葉に永い響きがあって、心が浄められ思いがする。
おのづから通ひなれたる道わびし遠き施設に
夫をおきて
体操する夫いくたびもふりかへりわれの所在
を確かむるらし
六日経て見まひしわれに見えがたき眼を向け
ぬ病み臥す夫は
わが夫もリーマン幾何の解明をなし得ず逝け
り寂しかりけん
トポロジー位相空間リーマン幾何夫の研究逝
きてより知る
ご主人は数学者であられたようだ。健康な頃のことを折々に思い起こしながら、老いゆく現実を見つめ、永訣に至るまでを詠じたこれらの作品には、作歌という営為の深さをつくづくと考えさせるものがある。
帰り来し子ら眠らんかひさびさに人の香のあ
る闇やはらかし
幼児はスキーたづさへいでゆけりかの近山も
吹雪きをらんに
ありし日の母のくれたる柱時計音すこやかに
四十年あり
ご家族を詠じた作には、随所で、近藤さんの人柄を思わせる感性が優しく働いている。
線量計つねたづさへて学校へ行くわがをとめ
すこやかにあれ
私ら子を産めますかと問ひたりし少女のあは
れ中学生とぞ
いちりん草咲き拡がれるわが庭を除染すると
ふ三年すぎて
原発事故に苦しみ日々を憂い過ごす人々、その一人として声を絞るように成したこれらの作品に対し、私は殆ど言葉を発し得ない。
遠くよりうねりつつくる高き波なぎさに朝の
ひかりを砕く
湖を見おろす牧場広々と草刈られゐてうごく
ものなし
経塚のめぐりは芽吹く楢木立はるのをはりの
光さびしく
身構えの無い眼差と穏やかな風趣を持味とするこうした作品の味わいは、旅先と住居地、日常と非日常の境を超えており、近藤さんが長年培ってきた作歌に対する信念のようなものが窺える。後記にも記されているように、この十年間は、近藤さんにとって悲しい出来事が多かったようだ。しかしながら、こうして一人のひたむきな生が綴られた歌集として世に送られ、やがては人々の心を充たしてくれるだろうことを思うと、何か胸に迫ってくるものがある。