この歌集は『雄のこゑ』『土明り』『空なほ遠く』に続く作者の第四歌集にあたり、平成二十一年から令和元年までの歌が収められている。
作者は愛知県蒲郡市在住で、国定公園に指定されている自然環境の中、海の見える山近くの蜜柑畑で永く蜜柑作りに勤しんでこられた。「歩道」平成二十七年九月号の「創刊七十年『歩道』と私(三)」に「短歌四十年『歩道』とともに」と題して作者が寄せた文の中に、「ただただ平凡と思われた毎日、忙しく働き子どもを育てる暮らしのなかに、詩があることを知ったよろこび。日常から逃れる術を願っていた私が、その日常のなかにこそ真実があり、詩があることに気付かされたのだ。これは私にとって大きな変革であった。」と述べている。蜜柑作りに半世紀もの間関わり続け、その真摯な生き方の中で、佐藤佐太郎に随順して自身の境涯に即して作歌活動を続け、純粋短歌の道を邁進してきた作者の本歌集は静かな声調で気品に溢れた作品に満ちている。
貧困の内にかがやく生のあり師の歌若きわれを支へき
暮れはやき蜜柑山より下りゆく茜広ごる空に向かひて
湖の辺にひと木たつ胡桃暮れゆく幹に水音ひびく
飼い猫など生き物に対する温かい眼差により感情豊かな作品が生まれた。
かたはらに坐れる猫はもの言はぬ賢者の眼にてわれを見上ぐも
歩み来る白き犬わが旧知にて脚よはき老をけふも伴ふ
もの言はぬ猫のぬくもり膝に置くかたみの思ひ分かつごとくに
帰り来し猫の足裏を拭きてやる雨に出でしをたしかめながら
最愛の母や夫にも作者の思いは深い。
臨終の母に告げたるわが言葉聞き留めたりや今に思ふも
やうやくに蜜柑の収穫終はらんと告ぐべき母はうつつに在らず
飯をへて炬燵にねむりゐる夫農に疲れし顔若からず
恙なく一年老いて峡畑に蜜柑摘みをり夫とわれと
自身を見つめた作品も印象深い。
過誤ひとつ思ひて長きひと日過ぐ梅の若葉に雨降りやまず
雨に籠り寒さにこもり家居する賜物のごときわが冬の日々
かにかくに働く者の自負のありけふの疲れに足りて眠らん
「この先どのような日々が訪れることか、想像できませんが、出来ることなら私の傍らにつねに短歌がありますように願うばかりです。」と後記にある。作者のご健勝とご健詠をお祈りする。
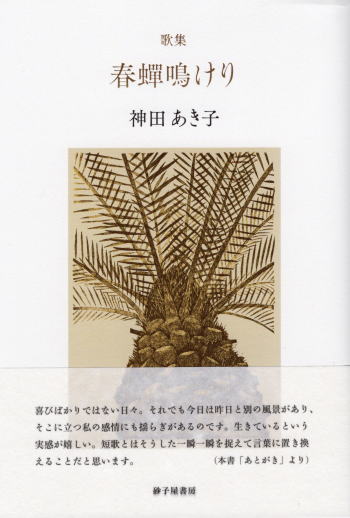 |