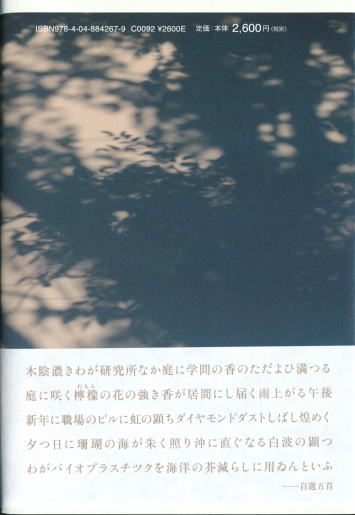土肥義治歌集『学問の香』を讃える
波 克彦
歌集『学問の香』は土肥義治氏の第一歌集で、平成二十二年から平成三十年までの九年間の作品五四八首を収めるとともに、平成二十五年から平成三十一年年初までの間に、業務の傍ら氏が発表した幾つかの随筆を合わせて随想付録として収めた意欲的な歌集である。
筆者と土肥氏とのお付き合いは、三十年余前に氏が東京工業大学の助教授時代に生分解性プラスチックの研究をしていたときに、会社で新事業開発を担当していた筆者が新しい生分解性プラスチックの研究委託をしたことに始まる。その後研究委託は終わりお付き合いは途絶えていた。そして二回目のお付き合いが、平成二十一年に、歌集の後記にもあるように、大学の同窓会である蔵前工業会の会誌に毎号作品を掲載している蔵前短歌会に氏が入会してきたことに始まる。筆者はその同窓会誌に掲載する短歌会作品の選者を務めていたが、氏が平成二十二年に同窓会の短歌会に作品を寄せて来たことから、本格的に作歌をするのであれば純粋短歌の道を進んでいる佐藤佐太郎先生創始の「歩道」に入会して秋葉先生に指導を仰ぎながら勉強するのが良いとお勧めしたところ、氏は躊躇することなく「歩道」に入会して現在に至っている。そして三回目は、氏が理化学研究所の研究担当理事で社会知創成事業本部長時代に、理化学研究所の研究について外部の有識者から意見を求めるために設置されたアドバイザリー・カウンシルの委員長に就任するように筆者に依頼するため筆者のいる米国法律事務所の東京事務所を訪問された平成二十二年であった。その折に氏から、理研の所内報をいただき、それに氏が寄稿した随筆により、氏が万葉集を研究して来たことを知り、氏の万葉集に関する造詣の深さを知った。
さて、本歌集を紐解くと、その作品群が、科学者の視点、研究機関の経営者の視点、そして万葉集の研究者の視点、日常の生活など多様性に富む視点から歌材が選ばれており、本歌集の題名「学問の香」がぴったりの歌集となっている。そして「歩道」入会当初からの作品を見ても、最初から充実しており、純粋短歌を指向する確かな眼、確かな把握がある。
例えば、平成二十二年の作品では、
谷川を見下ろしをれば
ほのかなる薔薇の香りをまとふ家窓のともしび花影映す
紅葉のモントリオールの丘に立つ街の喧騒届きてやまず
偉大なる科学者訪ねひと時の会談にしてわが課題知る
半生をかけてわが来し基礎科学その成果世に立つ時が来ぬ
科学者の見つけ出づる知組織にて融合しつつ社会知となる
また、日常の職場の木々や緑のキャンパスに学問の香を感じるという、緑豊かな研究環境に身を置いて来た作者ならではの感受である。
木陰濃きわが研究所なか庭に学問の香のただよひ満つる
カレツジの庭を横切る学徒ゐて緑の園に学問の香す
何しろ入会以来十年間の成長は著しい。それも以前から万葉集に親しんで来たことが純粋短歌の道にすすむ土台となっているからであろう。一首一首がすべて肯うことができ抄出することも難しいが、前出の歌のほかにも以下順を追って紙面の許す限り抄出する。これらの作品からわかる通り、氏の多様性が余すところなく表れている。
重責を終へんと語れば孫むすめ童謡うたひわれをねぎらふ
百合樹の冬の木立は天を突き高き梢にあまた実の立つ
生日に年金郵便とどきたり冬枯れの庭に赤き花咲く
来し日より帰る今日まで丘に咲くソウルの辛夷黄砂に霞む
ジヤスミンの垣根のつづく町を行くオリーブの丘糸杉の丘
秋日照る雲の上にて渡り鳥わが機の下をあまた飛び行く
歳晩に大日如来の御前にて科学技術の陽と陰を問ふ
大学の寮の跡地にひとり立ち来し方想ひ師に感謝する
淡江の直ぐなる光射す空にコーラン響きペナン明けゆく
アマゾンの森にあまねく川ありて豊かなる水いのち育む
ふる里の稲田の稔り黄に満ちて立山連峰むらさきけぶる
炭を焼くけむり漂ふ浅峡にまき割る音の乾きて響く
アジアより集ふ学徒に講義する科学史の間に万葉歌添へ
うつつにし見ゆる事実は真実の敵との教へ守り科学す
われは唯足るを知るとぞ思ひつつ石庭ながめ半時の過ぐ
僧院のなかの庭より見上ぐれば城塞つづく山に雷落つ
先進の科学における発見は再現を得て客観となる
アラビアの街角描くモンテイセリ人らの会話漏れくるごとし
自然にて起こる不思議を観察しその
台湾の老いし教授と対話して美しき和語を聞きて親しむ
蟬の音の替はる晩夏となりにけり道ゆく人の歩みの重し
客観の本質理解せざる徒ら科学の道をあゆむ能はず
ひもすがら英語の議論聞きをれば疲れ果てたりわが古稀思ふ
仕事場の難題かかへ帰りをり暮るる刈田に煙立つ見ゆ
百合の香のほのかに匂ふ湯の宿にメールの届き難題迫る
夕つかた子魚あまた跳ねひかる濠の水辺に花菖蒲咲く
篠山の
薄日差す空に立ちゐる原爆のドームにあまた赤蜻蛉とぶ
暮れ残る地平に出でし月影に放射光施設ほのかに明し
感性とわが身にて得し暗黙知創造力の源泉とせん
はるの夜に二両の列車里をゆく音と光を闇に残して
海峡に濃き霧低く立ちこめて塔のみ見ゆる明石大橋は
若き日に名付けしバイオプラスチツク世にし遍くその名広がる
衰へを自覚せしときロフトにて古き書籍を選び整理す
学生らと論じまとめし研究の記録叢書をわれいかにせん
本歌集を読んで心が安らぐのはなぜだろうか。筆者が氏と同じく技術系の人間だからであろうか。いや、本歌集を一読してさわやかに感じるのは、字余りを極力抑えてしっかりと定型を守ろうとする作歌姿勢にも依ると思う。その実直真面目な歌風にははや風格さえ感じられて頼もしい。
収載された短歌作品に加えて、収載されている随筆も作者ならではの真摯な把握に満ちていて大変興味深い。跋文で秋葉氏が指摘しているとおり、氏は既に堂々とした歌論を持っている。例えば、「創造的科学研究における直観と暗黙知の役割」と題する随筆にそれがしっかり示されている。少し引用すると。
「長年の鍛錬によって大脳皮質頭頂葉と大脳基底核が鍛えられ、とくに運動に係わる脳深部の基底核が最善手を直観的に導き出すのに重要な役割を果たしており、プロ棋士においてその働きが顕著であるという。このように、棋士の直観力は長年の経験と鍛錬の努力によって得られたものである。」、
「真実の発見が、科学における進化の動因となる。このような発見は精神における二つの行為によって行われるが、一つは理性による持続的行為であり、他は感性による瞬間的行為である。瞬間的行為が創造的直観であり、感性が隠れた真実を感じ取るのであろう。」、
「創造的科学研究においては、科学者の直観ともに暗黙知が重要な役割を果たしているようであろう。……ある個人が身体の五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)や運動、平衡、内臓の各感覚を通して習得し身体に蓄積保有している知恵や知識が経験知であり、この知の中に暗黙知がある。暗黙知は、自らは自覚していなくとも、身体が知っている知恵は知識であり、表出と伝達が不可能な知であるという。」、
「人は知りたいと思う事物の内部にまで身体感覚を延長し潜入させて、対象に主体的に係わり全感覚を働かせて、対象の全体性を捉えるという。この暗黙知が、科学者の独創性が創造的直観の源泉になるという。このように暗黙知は主観的な経験知であり、言葉や数式で表出され伝達できる客観的な理性知と対比できる。天才といわれる人たちは、ある事物に対する統合や潜入の度合いが強く、真理を探りつつ問題の本質を大局的に認識して、真実への発見物語を紡ぐのであろう」、
氏のこのような把握は、まさに大歌人である佐藤佐太郎先生について論述した文として読み替えることができる。筆者がかつて歩道誌に、「佐太郎の感性」と題して、第一歌集から第十三歌集までの佐太郎の歌の傾向を、直接体で知覚する感覚である「八感」(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、痛覚、温感、及び対内または体全体で感じる体感)に基づく作品について解析して作歌の変遷をたどろうとしたことと共通視点があり、筆者にとっても大変興味深い。
氏はこの随筆を、「抒情詩の世界において、斎藤茂吉は『実相に観入して自然・自己一元の生を写す』と定義した短歌における写生の説を唱えた。この実相に観入とは、対象の事物を心眼で把握することを意味しており、茂吉の造語である。短歌の実作にあたり、対象の認知的側面と情意的側面との言語表現の調和が重要である。認知的側面の表現は教え学ぶことができるが、情意的側面は自ら悟入する以外に方法はない。このように、暗黙知は自らの努力によって蓄積される経験知であり、芸術、文学、科学、技術など広い分野において創造力の源泉と基礎になっていると思う。」と閉じている。何と深い洞察であり、科学と文学の真髄を美事に言い得ている。
作者は実作において、既にこの認識を実践しようとしている。これから歩道を支えての活躍が強く期待される。