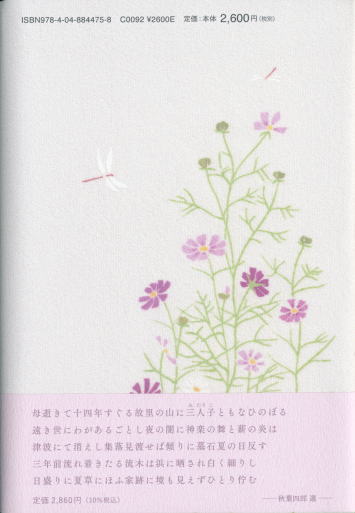大貫孝子歌集『家 跡』― 境涯の純粋短歌
土肥 義治
歌集『家跡』は大貫孝子さんの第一歌集であり、昭和五十五年から平成三十一年までの四十年近い年月の作品が収められている。大貫さんは昭和五十五年に「歩道短歌会」に入会し、盛岡支部「四季の会」にて短歌実践の研鑽を積まれた。その後、ご主人の転勤に伴い東京に転居され、東京歌会に参加しながら純粋短歌論に基づく作歌活動を継続されている。
大貫さんが作歌を始めたのは、結婚直後の二十代後半であったという。
朝市の買物をへて帰る道わが手をとりて夫はぢらふ
ぬばたまの夜空の遠き星見れば泰山木の大き白き芽
朝早く見送る夫の車よりまぶしき道に雪煙たつ
盛岡におけるご主人との静穏な生活の日常詠より歌集が始まる。三人のお嬢さんの成長を見守る母性歌、二〇一一年に故郷の女川町を襲った大震災と大津波被災の哀傷歌、犠牲者となったご両親への鎮魂歌、国内外の旅行詠や叙情歌、親族との交流や故郷の追憶に関する歌など作者の厳しくも豊かな半生を瑞々しい精神にて詩情豊かに謳いあげた多数の秀歌が収められている。
あとがきには、「全てが瓦傑となって変わり果てた故郷、影も形もなくなった家跡辺りを歩き、父継母を思い、そこで目に写した故里を短歌の器にこめて、歩道賞に応募したところ、震災三年後の平成二十六年、思いがけずに歩道賞をいただきました」と記されている。
まず、折に触れて詠ってきた三人のお嬢さんの誕生と成長に関する慈愛に満ちた母の歌を取り上げる。
夏の日の机の前にひとり居てかすかに感ず胎動の音
産着着てわが傍に動きなく眠りゐる児よわれは汝が母
たどり来て秋の日まぶしみどり児にわが乳あたふ無住の寺に
またひとつ新しき命たまはりてよこたふ吾に冬の日がさす
つづく咳しばしやみたる幼子の爪くれなゐに光る冬の夜
砂浜に幼らを呼ぶ夫のこゑ潮騒の中消えつつ聞こゆ
朝床に幼姉の手みどり児の手に触れ互みに笑ひあひをり
幼子は紋白蝶を追ひかけて山の道遠く小さくなりたり
音もなく雪降り続く長き夜ひたすら眠る三人のわが子
流れゆく光を追ひて川のべに子のすくひたる蛍のひかり
わが生の思ひ出ひとつ加はりて夜想曲子と連弾したり
反抗のあらはなる子の弾くピアノ隣の部屋にわれは聞き居り
わが側に子が音読す人生は五十年とふ徒然草を
娘住む酒蔵の街あゆみきて地下水をくむ白き月の夜
つぎに、胸に迫る悲しい大津波被災の哀傷歌を紹介する。海とともに生きてきた作者の故里女川町(人口八千人余)は、二〇一一年三月の東日本大震災による大津波に襲われ、人口の一割近い人々が犠牲となった。全壊家屋は三千余棟であったという。実家は跡形もなく消失し、ご両親は犠牲となり、家跡にて鎮魂の挽歌を詠み継いだ。
水とパン持ちつつ父と継母さがし変はりはてたる故郷あゆむ
うづたかき瓦礫の中に佇めば鉦をたたきて若き僧来る
避難所のひろき窓より中空に満月の見ゆ消灯のあと
怖れつつ棺を開けて水の浸む野良着を見れば確かに父なり
流されて身に着けしもの一枚の下着と指輪に継母を確かむ
ここに街ありしと後の世の人は語らん町に路のみ残る
廻りくる季節のあはれ家跡に去年のごとく蓬の萌ゆる
土台のみ残る家跡に集ひたる親族ら盆の迎へ火を焚く
津波にて消えし集落見渡せば傾りに墓石夏の日反す
点火せし線香をおき渚よりわたつみに祈る孟蘭盆の朝
冬の日の父母の墓のべ常のごと花の凍りて墓石光る
語部となりてわがをぢ訛りつつ大津波逃れし経験かたる
国内外の旅行にて詠まれた叙情歌や叙景歌も心を打つ。
ふるさとの冬山に似てかなしかり雑木林を透かす青空
遠き世にわがあるごとし夜の闇に神楽の舞と薪の炎は
海原をわたりくる風渚より砂をまきあげわれをすぎゆく
みちのくの光まぶしき道のべに母をしのびて山独活を買ふ
一人ゆく春の街寒く唐突に悔の湧き出で涙流るる
冬なれど暑き日をあびアスワンの赤さ真砂をわが手にすくふ
美しき運河にならぶ建物にアンネフランクの家さがしたり
モンパルナスの駅に聞こゆるピアノの音ふり向けばわが娘弾きをり
親族や友人を詠じた作品に大貫さんの温かい心情や人生の歩みを見ることができよう。
この父がわれの父なり藁をなふその手すばやく厚き手のひら
その妻をやさしく呼べる弟は故郷遠く広島に住む
聴覚を失ひし友としづかなる修道院に手話を習へり
この歌集は作者の半生を謳いあげていて、全ての読者に深い感銘を与えると思う。多くの方々の愛読を願う次第である。